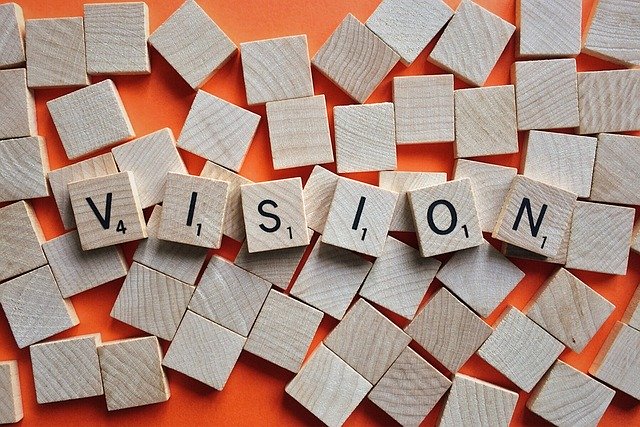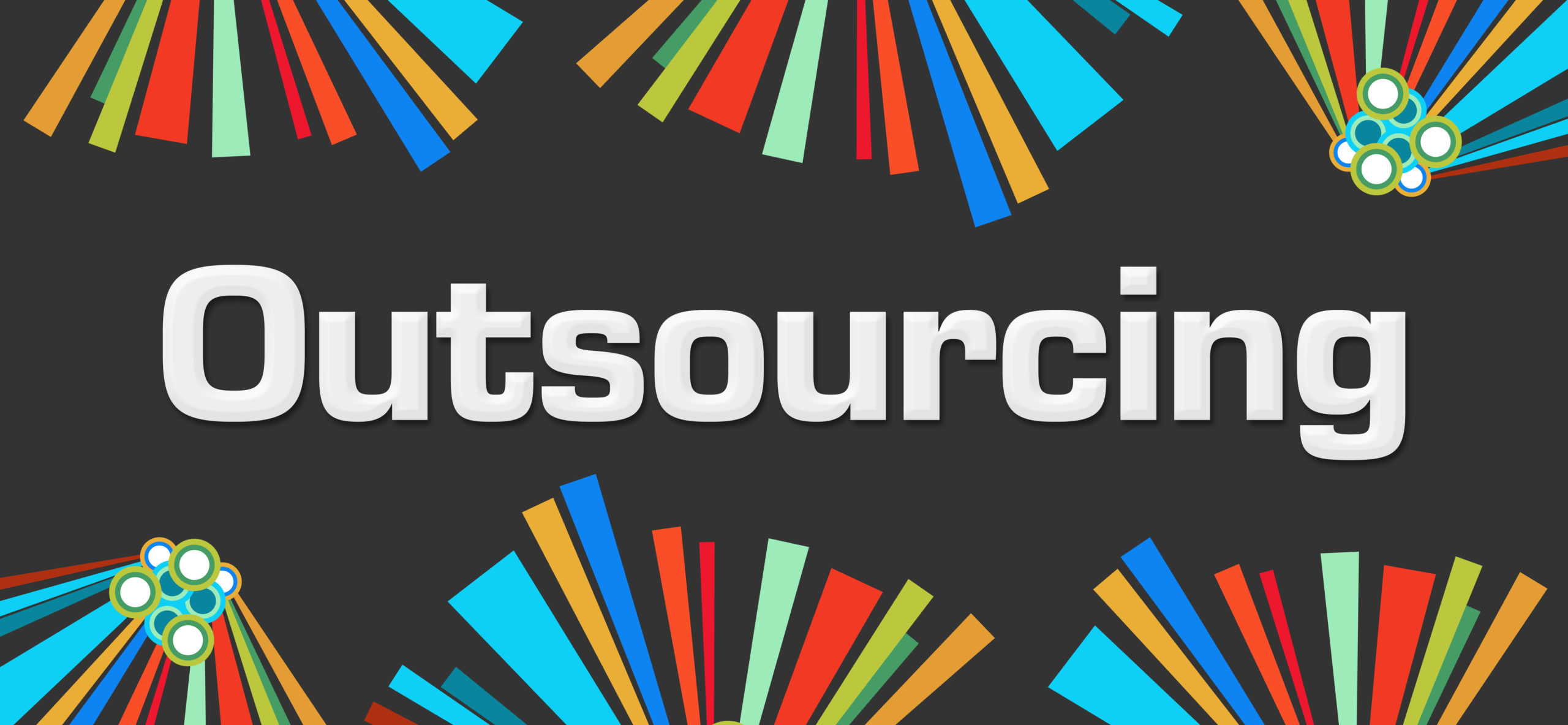離職率を改善したいBPOコールセンター現場
コールセンターBPOに業務委託をしている企業は多いですが、人材の定着が上手くいっているという現場は少ないです。
人材の流出が激しく、なかなか人が定着しない業務の現場では、最初のBPO選択の段階から間違っているケースが多々見られます。
例えば、
ITスキルを持った人が必要なサポート業務なのに、オペレーターの平均年齢が高く、求めるアウトプットがない。
落ち着いた丁寧な対応が必要なのに、平均年齢が低く、VIPのお客様に安心感を与えられない。
お堅い事業体にも関わらず、センター全体がくだけた印象・・・。
「そもそも、どうしてこのコールセンター現場を選択した?」
と感じるような選択ミスが多いです。
発注企業側に明確なビジョンがない!
このような選択ミスが起こる原因の一つとして、
発注する企業側に明確なビジョンがない!
ということが多々あります。
自分たちの事業がどういう事業で、どういうお客様をターゲットにし、どういうブランドイメージを作りたいのか?
ということがクリアに描けていないと、BPO社側からの提案もボンヤリとしたものになってしまいます。
特に、ブランド・イメージをハッキリと伝えた上で、各社からの提案を受けないといけません。
お客様と日々対応するオペレーターは、言わばその企業の”顔”となります。
コールセンター業界に長くいるので、
「業務のアウトソーシングを考えているんだけど、どこのBPO社がおススメですか?」
と、あらゆる人から聞かれることがあります。
決して、
「○○社がおススメです」
という答え方はしないです。
「どういう業務を委託したいですか?」
「どんな規模で、どんなアウトプットを期待していますか?」
などの質問をして、ニーズに合ったBPO社さんを紹介したり、お伝えしたりします。
どんなニーズにも応えられるBPO社など存在しません。
それぞれ、特徴、得意・不得意があるので、何を実現したいのか、ビジョンがまずありきなのです。
RFPの質で選択ミスを避ける!
※ RFP=Request for Proposal
最初の段階でボタンの掛け違いをすると、仕事を発注した方も、受けた方も後々不幸になります。
RFPにきちんとした要件を提示することが発注者として重要です。
更に注意したいのは、BPO社側もなかなか自信がなくても
「当社なら必ず期待に応えられます!」
的なセールス・ピッチは言ってきます。
営業は、新規クライアントを獲得することができれば、その後の業務については責任をほとんど持っていません。
一度契約してしまうと、後の運営は、現場の管理者と発注した企業の担当者の責務として、肩に重荷がのしかかってきます。
RFPには、どうしても守ってほしいことは、しっかり提示しておきましょう。
RFP作成のポイントは、こちらの記事も参考にしてみてください。
コールセンターBPOに任せてはいけない人選!
そして、最も大切なのは、やはり人材要件です。
コールセンターBPO社によっては、
「業務委託なので、採用・人材選択はこちらに任せてください!」
と言ってくることが多いです。
業務委託の経験が少ないと、
「そうか、相手はプロなんだから任せよう・・・。」
となってしまいます。
が、絶対に任せてはいけません。
特に、マネージャーやSVなどの管理職は、候補者を出してもらい、できれば面談しましょう。
彼らは、”企業の顔”として対応する人たちですから、本当に任せても大丈夫かどうかを確かめるべきです。
「業務委託なので、任せてください。」に絶対にのらないことです。
さらに、どういうオペレーターに対応してほしいのか、人物像やスキルを明確にしておきましょう。
もちろん、人材要件を厳しくすると値段も高くなったり、採用までのリードタイムにも影響します。
理想論ではなく、現実論のコミュニケーションが必要です。
理想の条件に対して、譲れる条件と絶対に譲れない条件をハッキリさせましょう。
例えば、パソコンの入力スピードについても、速いに越したことはないですが、業務によってはそこまで重要ではない場合もあります。
発注したい業務の必須要件を明確にすることで、採用ミスからの離職率を軽減できます。
「離職率はBPO社の責任」ではない!
発注者側としてよくあるダメな体質として、
「コールセンター現場の離職率改善は、BPO社の責任であって我々の知ったことではない。」
という対応が往々にしてあります。
離職率の改善は、より良い職場環境の構築です。
例えアウトソーシングで、他社の社員がオペレーションを実施していても、お客様から見たら1つの企業です。
コールセンターBPO社の現場を自社の一部として考え、離職率を軽減する意識が重要です。
離職率が高い原因の半分以上は、発注者側からの無理難題でもあります。
自分ができないことを他人に押し付けるのが業務委託ではありません。
その点を留意して、お互いにサポートし合いながら職場環境を作り上げる意識が必要です。