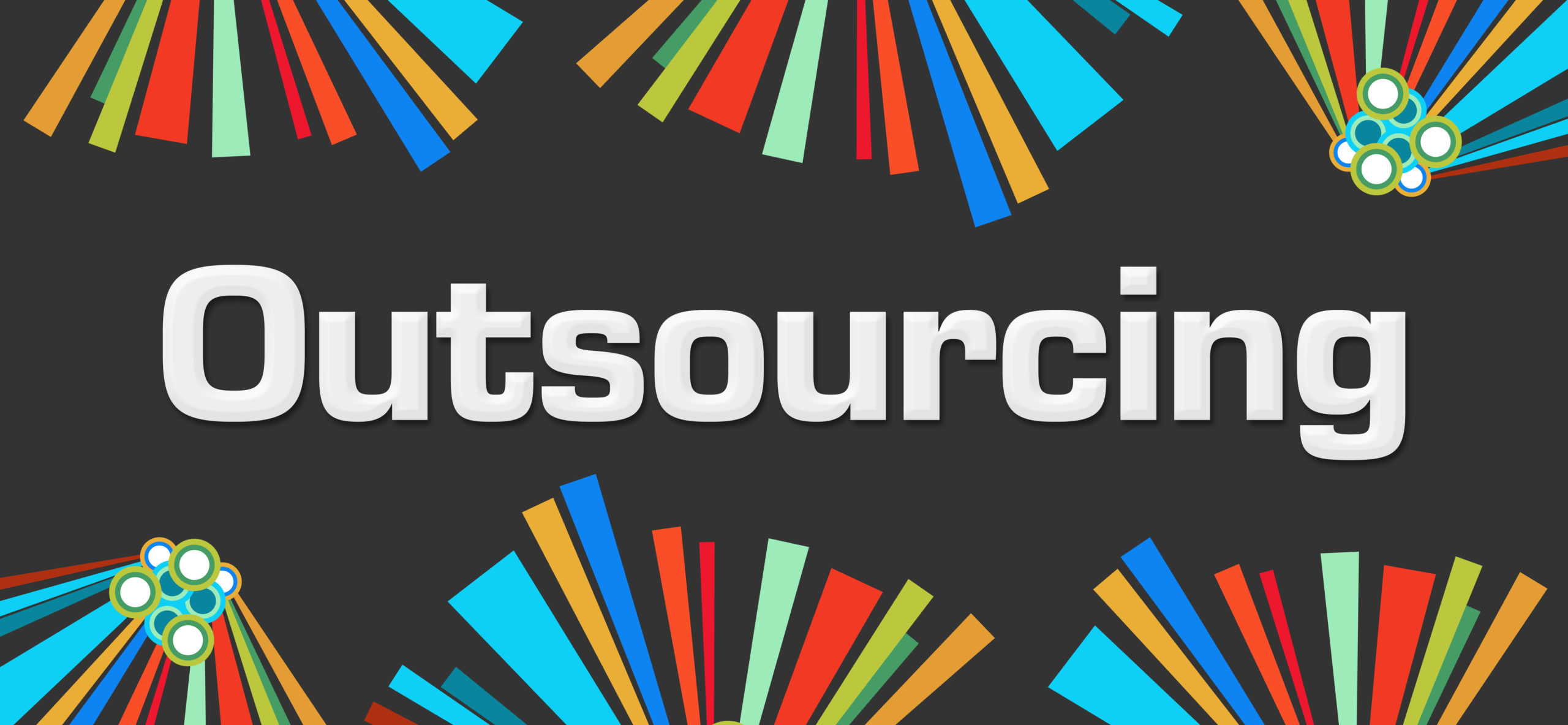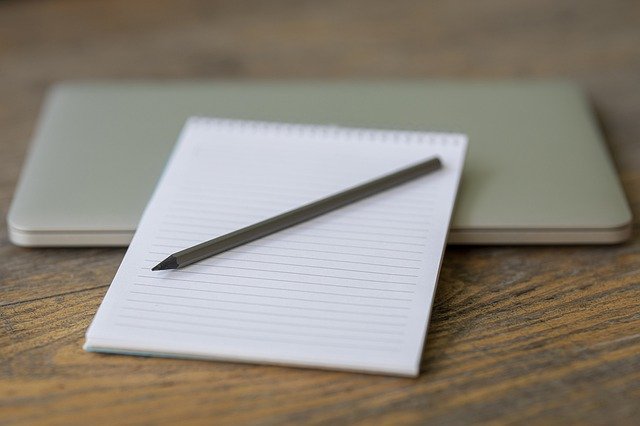BPOとは?
そもそもBPOとは、
B = Business(ビジネス)
P = Process(プロセス)
O = Outsourcing(アウトソーシング)
の略で、ビジネスの業務の一部を専門業者に委託することを言います。
BPOには、あらゆる種類のBPOがあり、ここで詳しくご説明しようとしているコールセンター のBPO以外にも、経理業務や書類審査業務、発送業務など、あらゆる業務を請け負う会社が存在します。
そういう専門分野を担当し、事業主から依頼を受けて仕事を実施るす会社のことをBPOと言います。
なぜ、BPOを使うの?
企業の本業ではないが必ず派生する事務処理等を専門の会社に委託することで、あらゆるメリットがあります。
企業がBPOを利用するきっかけや理由は下記の通りです。
1 その分野の専門家がいないため、立ち上げるのが難しい。
2 作業を他社に依頼することで、本業の力を入れたい。
3 自社で採用をするよりもコストが安い。
4 事業拡大に社内の機能だけでは、追いつかない。
5 繁閑対応が激しいため、リスクを軽減したい。
コールセンター BPOへアウトソーシングのニーズは?
コールセンター BPOを利用する企業は増えている一方で、BPOへの業務委託(アウトソーシング)で痛い経験をしたので、業務委託はしないという会社もあったりします。
一時期、コールセンター のアウトソーシングが流行し、BPOの業績はどこの企業も右肩上がりという時期がありましたが、その後、やはりインハウスに切り替えたという事業主も多くいます。
過去のBPO委託は、コスト面の理由や専門性という観点が多かったのですが、結局BPOへの委託がコスト削減に繋がらなかったという結果もあります。
反面、昨今では、外資系IT企業によるサービスの垂直立ち上げや急な事業拡張への対応を求める企業が増えてきています。
長年のBPOという仕組みの中でも、その内容やニーズは変化をしながらも、業界としては成長し続けていると言えます。
コールセンター BPOで働くって、どう?
コールセンター で働く場合、最初にBPOという選択は良いでしょう。
コールセンター の基礎知識のところでも、インハウスとBPOの違いについて述べていますが、コールセンター 運営の基礎的なことを広い視野で学びやすいのです。
基本的なトレーニングや評価基準がしっかりしているところが多いです。
また、中堅どころから大手のBPOは、全国に拠点を持っています。
家族の転勤や引っ越しなどが生じた場合も、ロケーションを変えて仕事をすることが可能になります。
また、BPOで正社員になると、転勤や配置換えなどが頻繁に起こるので、地方や違う土地で仕事をしてみたい人にはチャンスがありますね。
私自身も、新規センターの立ち上げで、2年札幌に住んだことがありました。
元々、北海道は出張で良く行っていたので、良い印象を持っていましたが、住んでみてさらに好きになりました。
できれば、老後は札幌に住みたいと思っています。
コールセンター BPOは、どこがいい?
コールセンター BPOの全国ランキングなどは、Googleで検索したら大手の名前がずらりと出てきます。
聞いたことがある名前もあるのではないでしょうか?
しかし、
「大手だから安心!」とは、一概には言えません。
前述したように、中堅から大手は、しっかりしたトレーニングプログラムを持っています。
ですが、”持っているだけ”というところも結構あります。
各社が保持している研修プログラムは、かなり多義に渡ります。
その中で、どのようなプログラムを用いて業務を遂行するかは、ある程度、各事業部の采配になっていることがあります。
つまり、事業のプログラムごとにいるオペレーション・マネージャやスーパバイザーが決めていることが多いのです。
コールセンターBPOのアルバイト面接で確認すること。
あなたが、これからアルバイトや契約社員としてBPOコールセンター で働くのであれば、ネットの口コミはもちろんのこと、面接では、下記のようなことをチェックしましょう。
- トレーニングは、どれくらいの期間でどのような内容か?
- 応対品質などの基本的なトレーニングがあるのか?
- シフト日時は、どのように決まるのか?
- 残業の量などは、どうなのか?
- オペレーターからリーダーやSVになる人がいるのか?
- チームの離職率はどれくらいか?
- 1人のリーダーは、何名くらいのオペレーターを管理しているのか?
最後の管理者の数は、ちょっと質問しにくいかもしれませんが、基本的に管理者1名に対してオペレーターが7名〜10名というのが適正です。
もちろん業務内容にもよりますが、1人の管理者が15名も見ているというような場合は、はっきり言ってオペレーターのスキル向上は無視されています。
アルバイトは放置されたまま、お客様対応ということです。
逆に、1管理者で3−4名しか見れていないというところも危険です。
オペレーションのフローが複雑であったり、システムによる効率化が図れていないチームなので、残業が多くなりがち。
適正なチーム運営がなされている部署で仕事をすることで、スキルアップへの早道となります。